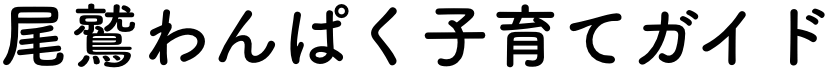児童扶養手当について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:8919
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成されている家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
受給できる方
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父又は児童を養育している人です。
なお、児童が、身体又は精神に中程度以上の障がいを有する場合は、手続きにより20歳未満まで手当の支給延長が認められます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年拘禁されている児童
- 母の婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
次のような場合は手当を受けることはできません。
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 児童入所施設に入所しているとき又は里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母が障がいを有する場合を除く)
父・母又は養育者が
- 日本国内に住所がないとき
手当を受ける手続き
手当を受けるには、住民地の市町で認定請求書に次の書類を添えて手続きして下さい。
(多気町を除く)町にお住まいの方は県知事の、市及び多気町にお住まいの方は市長等の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(添付省略できる場合があります。)
- 番号確認書類(個人番号カード・通知カード等) *同居している親族がいれば、その方の分も必要。
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
- 健康保険証(母または父および子ども)
- 預金通帳(母または父名義)
- その他必要書類
個人番号の記入について
新規認定請求書には請求者・対象児童・配偶者・同居の扶養義務者の個人番号を記入していただく必要があります。
また、請求者本人は個人番号カード、もしくは個人番号が確認できる書類及び本人確認書類(運転免許証など)を提示いただく必要があります。
手当の支払
手当は知事又は市長等の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払月の前月までの分が、受給者が指定した金融機関口座への振り込みにより支払われます(各月とも11日、11日が土、日、祝日の場合は、その日以前の金融機関の営業日)。
* 支払時期
5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回
手当の月額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得(1月から9月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得)により、全部支給、一部支給、全部停止の区分が決まります。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として年単位で支給月額を決定します。
| 区分 | 全部支給の方 | 一部支給の方 |
|---|---|---|
| 手当月額 第1子 | 46,690円 | 所得に応じて、 46,680円から11,010円までの 10円単位の額 |
| 手当月額 第2子 | 11,030円 | 所得に応じて、 11,020円から5,520円までの 10円単位の額 |
*一部支給の手当額の計算方法について
A:受給者の所得額
B:全部支給の所得制限限度額
第1子=46,680ー(AーB)×0.0256619
第2子以降=11,020ー(AーB)×0.0039568
※※ 児童扶養手当は、前年の全国消費者物価指数に対する前年の同指数の比率を踏まえ手当額の見直しがあります。
所得制限限度限度額について
| 扶養親族等の数 (税法上の人数) | 請求者(本人) | 孤児等の養育者、 配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給の 所得制限限度額 | 一部支給の 所得制限限度額 | ||
| 0人 | 69万円未満 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
| 3人以上 | 1人につき 38万円ずつ加算 | 1人につき 38万円ずつ加算 | 1人につき 38万円ずつ加算 |
※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
※老人扶養親族または同一生計配偶者(70歳以上の者)がある場合は、該当者1人につき、上記限度額に10万円
{配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者の場合は6万円(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)}、
特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額等)+*養育費-8万円ー*諸控除
*養育費……請求者が父又は母の場合、児童の母又は父からその児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品等の8割が養育費として所得に算入されます。
*諸控除
- 地方税法による控除
・医療費控除
・小規模企業共済等掛金控除
・配偶者特別控除
・肉用牛の売却による事業所得
2.障害者控除・・・・・・・・・・・27万円
(特別障害者控除・・・・・・・・40万円)
3.寡婦控除・・・・・・・・・・・・27万円
※受給者が母の場合は適用しません。
4.ひとり親控除・・・・・・・・・・35万円
※受給者が母または父の場合は適用しません。
5.勤労学生控除・・・・・・・・・・27万円
手当を受けている方の届出及び請求
| 現況届(すべての受給者) | 毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。 この届を出さないと、11月以降の手当が受けられません。 なお、2年間届け出をしないと受給資格を失います。 |
| 資格喪失届 | 受給資格がなくなったときに出します。 |
| 額改定(増額)請求書 | 対象児童が増えたときに出します。 |
| 額改定届(減額) | 対象児童が減ったときに出します。 |
| 受給者死亡届 | 受給者が死亡したときは、戸籍法の届け出義務者が出します。 |
| 変更届 | 同一市町内又は県内の町間での住所変更、氏名、銀行口座などを変更したときに出します。 |
| 転出届 | 他の市町(県内の町間の転出を除く)や他の県へ転出する場合に出します。 |
| 証書亡失届証書再発行申請書 | 手当証書を紛失した場合、また破損や汚れで使用できない場合に出します。 |
| 支給停止関係(発生・消滅・変更)届 | 所得の高い扶養義務者と同居又は別居するなど、現在の支給区分が変更となるときに出します。 |
受給資格がなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに市町へ届け出てください。 受給資格がなくなっているのに受給された手当は、全額返還していただくことになりますので充分ご留意ください。
- 児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日をむかえたとき
(心身に障がいがあるときは20歳になったとき) - 手当を受けている父又は母が婚姻したとき
(法律上の結婚だけでなく、内縁関係や生計を共にした時も含みます。) - 遺棄していた父又は母から連絡・訪問・送金があったとき
- 刑務所に拘禁されている父又は母が出所したとき(仮出所も含みます。)
- 児童が、受給者が母の場合は父と、受給者が父の場合は母と生計を共にするようになったとき
- 児童が施設に入所するとき、または里親に委託されたとき
- 養育者が児童と別居するようになったとき
- 母が受給者の場合、母が児童を監護しなくなったとき
- 父が受給者の場合、父が児童を監護しなくなるか生計を共にしなくなったとき
- 児童が死亡したとき
- 手当を受けている方が、平成26年11月以前に公的年金等の給付を受けることができるようになったとき(年金等請求手続きをとれば、受けられる場合も含みます。)
- なお、平成26年12月以降に公的年金等の給付を受けることができるようになった場合は、資格喪失とならず、手当額の支給制限が行われます。
- このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき