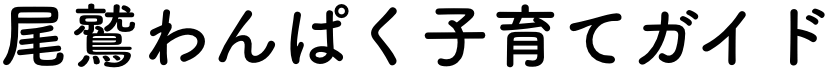6月まで ーその3ー
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:19041
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
きぐみだより 令和4年5月31日
メダカの卵が孵って赤ちゃんが産まれています。ジーっと飼育ケースを見つめ、赤ちゃんがどこにいるのか水面とにらめっこ。見つけると「いた!赤ちゃんかわいいね」と嬉しそうです。
さて、そろそろ梅雨入りかな?と思いますが、天気のいい日は、外で泥んこやお料理をして楽しんでいます。そして、5月後半から昼休みに学校の校庭へおじゃましています。小学生の遊んでいる様子をみたり、1年生と一緒に遊んだりすることが刺激になればと思っています。

楽しかった人?
はーい!
6月の目標
・身近な動植物に親しみ、その成長や変化に興味や関心を持つ。
・全身で水や砂に親しんで遊び、思う存分開放感を味わったり目的を持って繰り返し挑戦したりする。
~生き物や植物のお世話する姿から~
一匹のメダカの動きが他とは違っていたので、2人に声を掛けました。ケースを覗き込むと、「死んじゃうのかな?」「どうしたんだろう…」 「餌食べ過ぎて苦しいのかな?お水飲み過ぎたんかな?」 そんな会話をしながらもメダカを心配そうに見つめていました。翌朝、死んでしまったことを伝えると、動かなくなったメダカを見て「ここ見て!血が出てない?」 「ほんとだ!喧嘩したんだよ!」 「かわいそう…。」と言ってお墓を作ることになりました。お墓参りの経験や赤組の時にお墓を作った経験からか近くに咲いているお花を飾り、手を合わせました。生き物ですから、しっかりお世話をしていても死んでしまう、植物が枯れてしまうこともあります。お世話を「大変…」「面倒くさい…」と感じてしまうこともあると思いますが、頑張っている姿を認め「ありがとう。」「きれいにしてもらって喜んでいるよ。」などと声を掛けています。
生き物や野菜のお世話を通じて少しずつ、命の大切さ、尊さ、思いやりの気持ち、責任感を育んでいきます。大切にしようとする気持ちが、より深く考えることにも繋がります。絵本でも映像でもなく本物の生きたメダカや虫、植物とのかかわりは、たくさんの学びを与えてくれます。子どもたちが興味や関心が持てるように教師自身も子どもと一緒に生き物の飼育、お世話を楽しむようにしています。

お兄ちゃんがアオムシを分けてくれました。

うわー!うんちいっぱい!

きれいになったらメダカさん、喜ぶかな?

野菜の水やり。
「ここお水あげた?」
「まだ!」
「じゃあ、やっとくね」
『OK!ありがとう』
園長先生のご実家で貴重な体験をさせていただき、お茶が出来るまでの過程を知ることができました。たくさんほめてもらって…ご両親に感謝です。

上の2枚を積むんだね

たくさん積みました!

茶薫の香りを確認中!
「あっ、お茶みたいな
匂いがするね。」

交代しながら
茶薫を煎りました。

布袋に入れた茶薫を
手で揉みます。

後日、志保先生が干してくれていた
乾いた茶葉を飲む前にもう一度、
煎りました。
手で自分のほうに仰ぎながら
「うわーお茶の香りがする!」

「おいしーい!」

「最高!」
~おさすり作り~
中村山から戻ると、「いっぱいすることがある…。」と言うので、「じゃあどうする?作るのやめる?」と聞くと、「お家の人にもあげたいからやる!」自分たちでできるところは頑張って準備しました。生地を伸ばし、餡を包む作業は手際がよかったです。“美味しい”と言ってもらったことや自分のしたことが認められることって嬉しいですよね。

とげに気を付けてね。

洗うのは楽しい~

愛情もたっぷり入れておくね
17日給食参観はお忙しい中、ありがとうございました。とても静かなランチタイム。「黙食を徹底されているんですね。」と言っていただきましたが、「いやいや、2人の静かな姿にビックリしました!」
箸の持ち方や食べる時の姿勢などきちんと出来ていますが、時々、お椀を持つときに、4本指が上から縁を持つことがあります。その時には、正しいお椀の持ち方を指導していますが、園のお椀が大きくて手が小さい子どもには持ちにくいからかもしれません。お家では正しく持てていますか?雑巾絞りは、始めてからまだひと月しか経っていませんが、日に日に上手になっています。
~野菜の看板作り~

のこぎり1本ぎーこぎこ~
脚で板をしっかり押さえる。上手く出来て自信が
ついたそうちゃん。
「大きくなったら大工さんになろうかな?」
と考えていました。

かなづちトントン♪
釘が曲がってしまったら横から叩くと真っすぐになり
叩きやすいことが分かりました。
「ゆうちゃんすごい?」と覚えたワザを何度も使います。
おろし器で石鹸を削り、水を調整しながらネットや泡立て器を使ってクリーム作り

こどもビールで~す

ケーキ作ってるのよ

ウォーターサーバーです
空き箱で作ったんだよ!

梅雨のような雨が続き、遊園地を開園しました!

それぞれが自分専用のお風呂を作りました。
最終的にはトンネルを掘り3つとも繋げました。

砂場から水道まで「よーいどん」
3人が水道めがけてダッシュ!
教師が先に汲んでいるのに、
横入りして「お先に~」と、
とびっきりの笑顔で去っていくんですよ!」

この後ろ姿、見覚えが…。
世古さんとちーちゃんが
遊びに来てくれました。
5/24 三木峠・羽後峠に挑戦!

三木峠入口
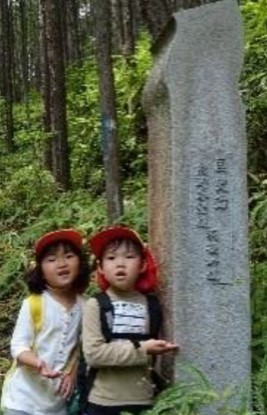
羽後峠入口
初めは、三木里にある「三木峠」から登りました。
2つとも、小さな峠で比較的緩やかな道です。コケが生えた石段道が続き、まるでジブリの世界に出てくる森のようで幻想的です。時折、木々の間から海が見えて
楽しいコースでした。三木峠を下りてから農道を30分ほど歩きましたが、羽後峠を歩き始めると元気復活。
お弁当は「森のレストラン」のような広場で食べました。
帰り道、そうすけ君が「スギ葉だ!」とスギ葉が落ちていることに気づきました。自然体験で火おこしに使ったことを思い出したようです。“森じーにお土産にしよう”と
みんなでたくさん拾いました。(笑)後日、森じーに届けに行くととても喜んでくれました。しばらく歩くと羽後峠には、石垣が連なる見事な“猪垣”が見られます。なぜ石垣が続いているのか、昔の人の暮らしに想いを馳せ、歩きながら考えました。ゆうひちゃんが、「わかった!山から落ちた時に下まで転がっていかないようにじゃない?」答えが合っているかどうかではなく、いろいろ考えたり、感じたり、思ったりすることを大切にしたいです。
石垣が続いているのはなぜか、お子さんに聞いてみてね。

石をたくさん積んでいるのはどうしてかな?

イノシシやシカに田畑を
荒らされて困っていた人
たちが…


2人のつぶやきから
部屋の中にさーっと風が入ってきて、てるてる坊主を吊るしているテープが音を立てながらてるてる坊主が揺れていました。
ゆ:「寒いよう…って言ってるのかな?」
そ:「違うよ。明日、天気になるようにって、パワーを送っているんだよ。」
2人のてるてる坊主の気持ちを身振り手振りで表現する姿に癒されました。
5/30 第2回 自然体験/レゴで遊ぼう!
初めてのハーネス体験。大学生のお兄ちゃんたちに2人の様子を伺ったところ怖がることなく平常心だったそうです。大人に手を繋いでもらうのとは違い、「自分の力で下りることで、“自分でやったという達成感に繋がる”道具(ハーネス)を使うことで楽になる。という体験をしました。森田さんは、磯場で遊ぶ、おやつを食べるなど子どもたちが楽しめるように変化をつけてくれていましたが、ビーチグラスを拾う時の2人の集中力の高さをほめてもらいました。レゴ遊びは、“かたつむり作り”は難しかったけれど、たろにーの手元をじーっと見ていて、“見る力が前回よりもついているね”とみなさんに言っていただきました。「できない、やって」と弱音をはくこともなく自分の力で作りたいという思いが伝わりました。

ガードレール脇から浜までハーネスを装着し、
1人ずつ浜まで下りました。
森じーとロープで繋がっていて、大学生のお
兄ちゃんが付いてくれたから安心して下るこ
とができました。

ウニを手に乗せたよ~「ちくちくしてくすぐったい」
~自然体験・レゴ(大学生に学びながらの)遊びを通して~
eSTEM(イーステム教育)って聞いたことがありますか?これからの社会を生き抜くために必要な力を身につけることができる教育モデルであり、技術の向上だけでなく、環境に配慮したより良い社会を作れる人材の育成。根本には「自分で学び、自分で理解していく子ども」を育てるねらいがあり、新たな時代に必要とされる自発性、創造性、判断力問題解決力を養う。 e…環境教育 S…科学 T…技術 E…工学 M…数学
今回、レゴのパーツが組み立て方によって可動する、シーグラスをレンジで溶かして変形させられること(科学サイエンス)を知りました。毎回、自分が体験したことをフィールドバックさせるためにレゴを使っていく。大学生さんとのかかわりも子どもにとって
重要で、思いや形が定まる前の子どもたちにとって自己実現が形になる。自発的に学ぶ、自分で理解する、自分で発見していく力をつけておけば、やがて独自の創造性を発揮することにも繋がるそうです。18歳くらいまでに、それらの力を持っておくと自分の進みたい進路が定まる、社会に出た時の強みになる。今の2人にとって“今日は楽しかったね”と終わっても体験・経験が繋がっていけば力になっていく。みなさんとの振り返りや今後の話し合いの中で色々な話を聴かせていただきました。少し難しい話になりましたが、2人の将来に繋がるとても貴重な経験をさせてもらっていていると改めて感じました。

3回目は6/27(月)です